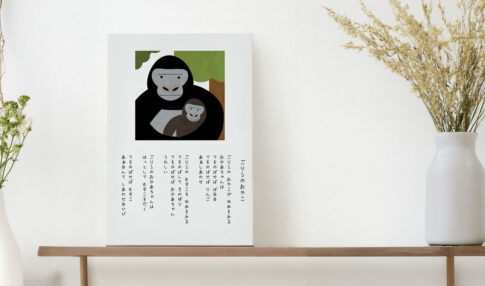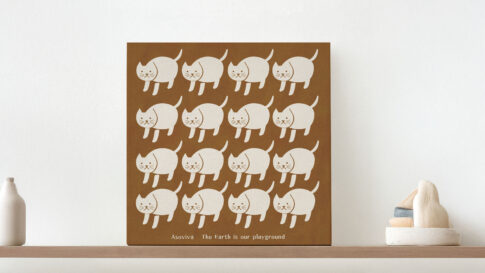北欧の静けさと、日本の民芸のあたたかさ。どちらも、自然と寄り添いながら
暮らしの中に美しさを見つける心を大切にしている。
暮らしの中に美しさを見つける心を大切にしている。
なので、日本の民芸と北欧デザイン、
この二つは遠く離れた土地で生まれたのに「驚くほど似た美意識」があるんです。
その共通点の一つが、
使うための美しさを大切にするところ。
日本の民芸運動を始めた柳宗悦は、
「日々の暮らしで使われるものにこそ美が宿る」
と考えていたそうです。
そして北欧でも、「美しいものは実用的であるべき」
という同じような考え方がデザインの根幹にあるようです。
北欧家具の名作チェアや日本の益子焼の器など、
どちらも“飾るため”ではなく
“使うため”の美しさがあってうなずけます。
そのほかにも、お互いに自然素材を取り入れる(土、和紙)や
(木材やリネン)など自然との調和を大切にしているところなども共通しているところ、
シンプルで、素朴で、けれどどこか凛とした存在感がある。
でも一番なるほどって思ったのが、
お互いに「余白の美」を大切にしているところ、
日本の「間(ま)」と北欧の「ヒュッゲ(心地よさ)」と
どちらも“静けさの中の豊かさ”を大切にしている言葉。
北欧の白い壁や日本の畳の空間などの余韻のデザインは
どちらも派手さではなくても、余白や空気感で心を落ち着かせる。
木のぬくもり、手仕事の跡、
やわらかな光が生まれる空間には、
国を超えて通じ合う“静かな美”が息づいている。
北欧と日本、二つのデザインが響きあう場所に、
暮らしをやさしく包む色があるんだな。